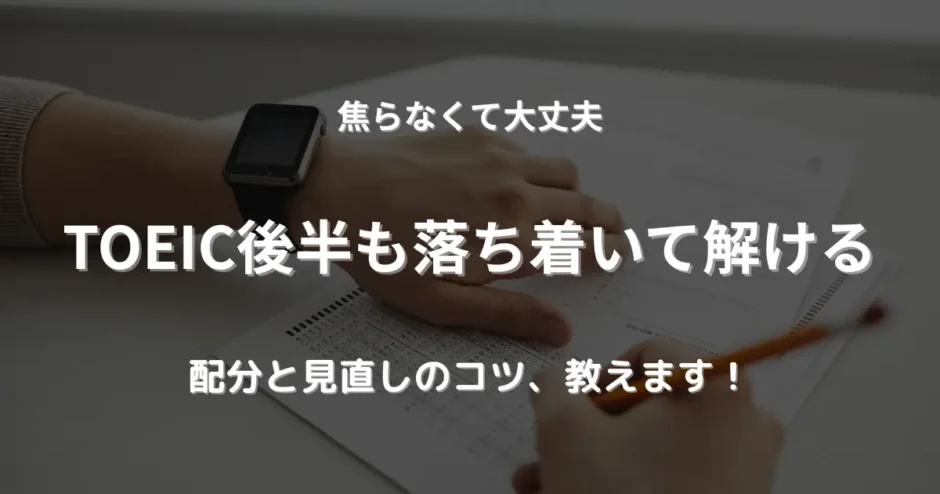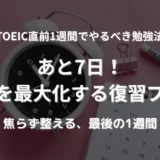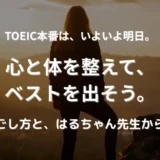こんにちは、今日も英語勉強中のはるちゃん先生です。
TOEICの模試や本番で、「あと◯問あるのに、もうこんな時間!?」と焦ってしまったこと、ありませんか?
はるちゃん先生も、何度も模試で時間切れ→ケアレスミス→悔しい失点を繰り返してきました。
特にリーディングは、実力があっても時間配分に失敗するとスコアが伸びないのがつらいところ。
でもある時、原因と傾向を分析して、自分なりの「時間配分&見直しルール」を作ったことで、最後のトリプルパッセージまで落ち着いて解き切れるようになったんです。
この記事では、そんな体験ベースの工夫と、再現しやすい時間管理のコツをギュッとまとめてご紹介します!
- TOEICリーディングで時間切れしやすい原因と対策
- パート別の時間配分の目安と解き方のコツ
- 設問181以降で集中力を保つ“切り替えポイント”とは?
- 本番で焦らないための「見直し術」と「心の準備」
まずはここから!TOEIC各パートの時間配分の目安
TOEICのリーディングセクション(Part5~7)は、75分の中で100問をどう攻略するかがスコアアップのカギ。
実際に何度も模試を受けて気づいたのですが、「なんとなくのペース配分」では確実にPart7で時間が足りなくなります。
とくに後半のトリプルパッセージでは、集中力も体力も落ちてくるので、計画的に“時間を残しておく”ことが本当に大事なんです。
そこで、はるちゃん先生がたどりついたパート別の時間配分の目安と、それぞれのポイントを表にまとめました👇
| パート | 時間の目安 | ポイント |
|---|---|---|
| Part5(短文穴埋め) | 約10分 | 「10・10・5秒ルール」で即決力UP。文構造→選択肢→決断をテンポよく。 |
| Part6(長文穴埋め) | 約8分 | 文脈理解がカギ。設問タイプ(語彙・文選択・一文挿入など)で緩急をつける。 |
| Part7(長文読解) | 約55分 | シングル・ダブル・トリプルで時間を配分。設問181に入る時点で26分以上を目標に! |
それぞれのパートで意識していること

Part5:テンポよく解く「10・10・5秒ルール」
はるちゃん先生は、Part5で1問30秒を超えそうになったら「切り替え!」の合図と決めています。
- 最初の10秒で文構造(主語・動詞・空所の役割)を確認
- 次の10秒で選択肢を比較して絞り込み
- 最後の5秒で決断→マーク→即次へ!
分析する前は、ただただ、「早く解かないと!」と焦っていたので、ちゃんと文章を全部読まずに答えていたところも…。
でも、「25秒は使えるんだ」と、解く時間を意識するようになってからは、落ち着いて問題文を確認できるようになってきました。
加えて、意外と時間を使わずに解ける問題が多いことにも気づけました。
それを踏まえて、もし迷ったら、「今ここで1問を取りにいくより、Part7に時間を残す」ことを優先します。
※この意識だけで、リーディング全体の安定感がかなり変わりました!
TOEIC Part5の対策に関する記事はコチラ▼
Part6:文の流れを感じつつ、設問タイプで緩急を
Part6は、文脈理解が問われるので、Part5のように機械的には解けません。
でも、設問タイプによっては時短できます。
- 単語・接続詞:Part5感覚でテンポよく
- 一文挿入:前後を丁寧に読んで判断(時間をかける価値アリ)
目安は1問30秒×4問×4セットで8分。
ここで焦らず、でも時間をかけすぎずにいけると、Part7への良い流れが作れます!
Part7:勝負どころ!セクションごとの配分を意識
Part7はシングル→ダブル→トリプルの順で登場し、だんだん難しく・情報量も増えていきます。
はるちゃん先生の目標配分はこんな感じ↓
- シングル(設問147~176):約30分
- ダブル(177~185):約10分
- トリプル(186~200):約15分(ここが一番ハード!)
設問181に入る時点で26分以上残っているか?を毎回チェックするようにしています。
(もし22分以下だったら、次の模試はペース改善が必要サイン!)
TOEIC Part7の対策に関する記事はコチラ▼
このように、それぞれのパートに「時間の使い方の型」を作ることが、焦らず最後まで解ききるための第一歩。
次のセクションでは、特に重要なPart7の後半で時間を守るためのコツを深掘りしていきますね!
Part7後半の20問が勝負!リーディング成功の分かれ道
TOEICのリーディングパートは、時間との戦い。
特に設問181〜200の後半ゾーン(ダブル・トリプルパッセージ)は、文章量・情報量ともに圧倒的です。
このゾーンをどう乗り切るかが、スコアに直結します。
理想は「設問181時点で26〜30分残し」

後半20問を解くためには、最低26分、できれば30分残っているのが理想的です。
以下は、おおよその時間配分の目安です:
| セクション | 設問範囲 | 内容 | 理想時間 |
|---|---|---|---|
| ダブルパッセージ② | 181〜185 | 2文書+5問 | 6〜7分 |
| トリプルパッセージ① | 186〜190 | 3文書+5問 | 約8分 |
| トリプルパッセージ② | 191〜195 | 3文書+5問 | 約8分 |
| トリプルパッセージ③ | 196〜200 | 3文書+5問(最難関) | 約8分 |
30分残しができると、焦らず読み切る余裕ができ、最後に見直しの1〜2分も確保できます。
後半は「設問→本文読み」に切り替えよう
前半は「本文→設問読み」でもOKですが、181番以降は読み方の切り替えがカギです。
はるちゃん先生自身はというと、前半は本文を先に読んで設問に答えていくスタイルなのですが、後半はあえて「設問→本文読み」に切り替えています。
なぜ「設問→本文」がいいの?
- 目的をもって読むことでムダ読みを防げる
- 何を探すかが明確になる
- 集中力が落ちても「情報検索モード」に入れる
- 複数文書からの出典確認問題に対応しやすい
ポイントは「何が問われているか」の分類
設問を見たら、以下のように頭の中でラベリングすると、読みやすさがアップします:
- 誰が何をした? → 【人物系】
- どの文書に書かれている? → 【出典確認】
- なぜそうなった? → 【理由・目的】
- 数字・時間・日付 → 【具体情報系】
ラストで焦らないために「声かけ」で気持ちを切り替える
はるちゃん先生スタイルだと、後半の設問に入る前、ちょっと深呼吸して、「ここからは設問読みモード!」と心の中で宣言すると、意識が切り替わって落ち着いて読めます。
これは、特に集中力が切れてくる後半のメンタルコントロールとしてとても有効です。
- 「あとひと踏ん張り。落ち着いていこう」
- 「急がない。落ち着いて選べば大丈夫」
こんな感じで、事前に自分に合う声かけフレーズを1つだけ決めておくと、本番でも使いやすいです。

まるでスタートの合図のように、「181番に入る前に唱えるルーチン」にすると、気持ちが切り替わってミスが減ります。
Part7後半の攻略まとめ|時間と読み方を味方にしよう
| 観点 | ポイント |
|---|---|
| 時間配分 | 設問181に入るときに26〜30分を残す |
| 読み方 | 「設問→本文」読みで検索型の読解に切り替える |
| 集中のコツ | 設問の種類を意識し、答えを探しにいく姿勢を保つ |
| メンタル対策 | 後半に入るタイミングで意識をリセット |
見直しのコツは「問題に戻らない」「マークを守る」
「見直し時間=問題を解き直す時間」と考えがちですが、はるちゃん先生はあえて“問題には戻らない”スタンスでいます。
なぜなら――本番中の3〜5分という限られた見直し時間で、もう一度読み直して正答にたどり着ける可能性は低いからです。
見直し時間は「3〜5分」が理想
設問200まで解き終えたら、最低でも3分は残したいところ。
この時間でやるべきことはただひとつ。
「マークミスを防ぐ」こと!
内容に自信がある問題でも、マーク欄が1段ズレていたら不正解…なんて悲しすぎますよね。
見直しの最優先は「マーク欄の確認」
はるちゃん先生がやっている見直しルーチンはこちら:
- 181〜200の20問をざっとスキャン
- マークが全部塗られているか確認
- ズレがないか、1問ずつ目で追って確認
- 時間があれば150番から順にマーク欄だけもう一周チェック!
「正解できてたのにマークミスで落とした…」という失点を防ぐためにも、最後は“塗り”に集中!
「そうそうマークミスなんてしないでしょう?」と思うかもしれませんが、はるちゃん先生は、だいたい毎回あります…。
不思議なほど、ポコッと一問塗り忘れていたりするので、チェック必須です。
迷った問題には戻らない方が正解かも?
「うーん、BにしたけどDだったかも…?」
そんなふうに迷ったとき、戻って変えるべきでしょうか?
実は――
最初に選んだ答えの方が正答率が高いという研究結果もあるんです!
本番中のあなたは、それまでの文脈や感覚で最も“正解に近い”選択肢を選んでいることが多いんです。
だからこそ、最後の見直しで根拠のない変更はせず、「自分を信じてそのままにする」ことが結果的に高得点につながります。
「変えない勇気」と「整える見直し」で最後まで得点を守ろう
TOEICの見直し時間は、逆転のチャンスというより“スコアを守る最後の砦”。
- マークミスを防ぐ
- 焦ってマーク忘れた箇所を埋める
- 自信を持って選んだ答えはそのままにする
この3つができれば、見直し時間は完璧です!
「問題に戻らず、マークを守る」
これが、はるちゃん先生のTOEIC本番で焦らない見直し術です。
まとめ|TOEIC本番で焦らないために、時間配分と見直しの習慣を
TOEICのリーディング時間配分や見直し術は、「英語力」だけではなく「戦い方の工夫」で大きく変わります。

特にPart7後半では、気力・体力との勝負にもなりますが、
- 「〇分で〇問」などのルールを決める
- 自分なりの声かけや見直しポイントを習慣化する
といった工夫だけでも、本番での安定感はぐっと増します。
模試での失敗や息切れも、工夫次第で「次はこうしよう」と学びに変えられる!
本番で焦らない自分を作るには、事前のシミュレーションとちょっとした仕組みがとても大事。
せっかく頑張って積み上げてきた英語力。
自分に合った戦い方を見つけて、今までに身に着けた英語力を出し切りしましょう。
はるちゃん先生といっしょにね。
 はるちゃん先生は今日も英語勉強中
はるちゃん先生は今日も英語勉強中